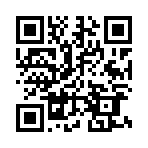2011年12月14日
第2回 春(スプリング・シーズン)
バスの習性でも絶対に理解するべきもののなかに、シーズナル・パターンが
あります。
バスも四季のあるフィールドに生息していますので、季節の変化に影響され
ない訳はありません。この季節によって変化するバスの行動パターンをシーズ
ナル・パターンといい、これを理解することが成功の早道といっても過言では
ありません。
今回はその中でも、一番イベント性が高い春(スプリング・シーズン)に
ついて述べようと思います。
春には1年を通じて最も大きなイベント、スポーニング(産卵)があります。
この時期に釣れるバスは、産卵に関係しているため、良型~大型が多く、ラン
カーサイズをゲットする一番良い季節とも言えるでしょう

スプリング・シーズンの乙女が池
このスポーニングには大きく分けて、プリスポーン、スポーニング中期、
アフタースポーンの3つの時期に分かれます。それぞれの時期によって攻め方が
違うので、自分の通うフィールドがどの時期に当たるかを知ることは非常に大切
です。せっかく正解のポイントに入れたとしても、間違った攻め方をしてボウズ
ってことも往々にしてあります
<プリスポーン>
プリスポーンは、産卵を控えたバスが栄養を取るために荒食いする時期です。
成書には、いろいろなルアーに反応するので、広く攻めるルアーを選択するべき
と記載があります。しかし、それはバスボートに乗って広く探るときに当てはま
ることで、フローターやオカッパリではなかなか困難なことです(夜釣りで岸際
に回遊してくるバスを狙うのなら別ですが)。
このときに有効になるのが、コンタクト・ポイントを見極めるということです。
プレスポーンで荒食いをして栄養を蓄えたバスはスポーニング・ベッド(産卵床)
を作る浅場に向かう前に、あるポイントにステイします。これがコンタクト・
ポイントです。沖での荒食いを終えているとはいえ、コンタクト・ポイントにステイ
しているバスの活性は高く、高確率で大型がヒットしてきます。
コンタクト・ポイントは人工的な構造物の場合もあれば、葦際の場合もあります。
フローターやオカッパリでも狙える場所も多いので、それぞれのフィールドでどこが
コンタクト・ポイントなのかを知るバサーだけが至福の時を迎えるのです

コンタクト・ポイントでヒットしたプリスポーンのバス(2010年3月、55㎝、琵琶湖北湖)
コンタクト・ポイントの攻め方は、ピンポイントを狙うので、ワームの釣りが
主体となります。リグの種類は縦に誘うことができるものが良いでしょう。ここに
ステイしているバスは上から落ちてくるものに反応しやすい傾向にあります。
ワームの種類や大きさは千差万別。実際に試してヒットするワームが正解だといえます。
そのフィールドに詳しいバサーに聞くのが一番簡単ですが教えてくれるかどうか
<スポーニング中期>
コンタクト・ポイントから離れたバスは、水深1~2mの浅場に入り、スポー
ニング・ベッドを作り産卵します。このスポーニング中期のバス達は雄雌のペア
か、超大型の雄に複数の雌が付き添っていてハーレムを作っている状態が多いで
すね。

ハーレムを作っていた雄バス(2011年5月、63㎝・6.5lb、乙女が池)

抱卵した雌バス(2011年5月、56㎝・5.5lb、乙女が池)
一度、スポーニング・ベッドを作ったバスはなかなか捕食行動に出ずに、スポー
ニング・ベッドに侵入してくる外敵に攻撃を繰り返します。このバスを食性で釣る
のは非常に困難ですので、この攻撃性を逆手にとって、バスをヒットさせる方法が
あります。
成書にはサスペンドミノーを使い、あたかもスポーニング・ベッドを狙っていると
バスに思わせ、攻撃したときに引っかけるようにヒットさせるとあります。
これも一つの方法ですが、スポーニング・ベッドを守っているバスといえども、
ほんの少し食性は残っているので、それに訴えるリグとルアーを選んでヒットさせる
方法と、攻撃性があるバスをもっと怒らせてヒットに持ち込む方法もあります。
こちらの方がサスペンドミノーを使うよりヒットする確率が高いのですが、ここでは
秘密とさせてください(フィールドでお会いすることがあればご紹介できますが)
<アフタースポーン>
産卵を終えた雌バスは、体力を回復させるために直ぐに沖に移動しますが、長く
スポーニング・ベッドを守っていた雄バスは、体力を回復させるために岸際のスト
ラクチャーにステイします。これがアフタースポーンの雄バスですが、喰い気は
あるものの、かなり警戒心が強く、少しの違和感がだけでヒットしてきません。
オカッパリやフローターでアフタースポーンの雄バスを釣るには、ロングディス
タンス・フィネスが有効です。気配を消して、なるべく遠くから極軽い仕掛けで
バスの前にワームをプレゼンテーションさせます。アクションは小さくしてアピー
ルし過ぎないように気を付けます。当然、ワームは小さめが良いし、カラーも
ナチュラル系が有利だと思います。確率は高くないけれど、ヒットさせることは
できますね。
この時期にヒットするバスは痩せていて、可哀想なくらい貧弱な印象を受けますが、
結構引きは良いですね。

痩せたスレンダーボディの雄バス(2011年6月、56㎝・4lb、琵琶湖北湖)
以上がスポーニングの攻め方ですが、何といっても、コンタクト・ポイントを攻める
のが一番良い方法です。コンタクト・ポイントの見極めが勝敗を決するのです。
☆雌バスの産卵回数は一回だけですか?☆
雌バスは何回産卵をするのかご存じでしょうか?
雌バスは一度に産卵するのではなくて、数回に分けて産卵します。つまり、産卵を
する1個体が何回か、沖→コンタクト・ポイント→スポーニング・ベッド→沖の移動
を繰り返すのです。
ここで、注意するべきは、コンタクト・ポイントにアタリが無くなっても、数日で
第2波、第3波と違うグループがコンタクト・ポイントに入って来て、アタリが復活
するということです。コンタクト・ポイントで良い釣りができる期間は意外と長いの
です。
スポーニング真っ盛りの時に、コンタクト・ポイントがノーマークになっていること
が多いので、チェックするのを忘れないようにしましょう
☆スポーニングは一斉に起こるんですか?☆
スポーニングはその地域一斉で起こる訳ではありません。私の通っているフィールド
でも、10km圏内で、早いところ遅いところで2ヶ月くらいの開きがあります。
それぞれのポイントのスポーニング開始時期を把握していると、美味しい時期を逃さ
なくてすみますね。そして、早いポイントから遅いポイントへ時期をずらして探って
いけば、長い間、デカバスに出会える機会を楽しむことができますよ
次回は、難敵の夏(サマー・シーズン)です。いろいろと誤解も多い時期なのですよ。
あります。
バスも四季のあるフィールドに生息していますので、季節の変化に影響され
ない訳はありません。この季節によって変化するバスの行動パターンをシーズ
ナル・パターンといい、これを理解することが成功の早道といっても過言では
ありません。
今回はその中でも、一番イベント性が高い春(スプリング・シーズン)に
ついて述べようと思います。
春には1年を通じて最も大きなイベント、スポーニング(産卵)があります。
この時期に釣れるバスは、産卵に関係しているため、良型~大型が多く、ラン
カーサイズをゲットする一番良い季節とも言えるでしょう


スプリング・シーズンの乙女が池
このスポーニングには大きく分けて、プリスポーン、スポーニング中期、
アフタースポーンの3つの時期に分かれます。それぞれの時期によって攻め方が
違うので、自分の通うフィールドがどの時期に当たるかを知ることは非常に大切
です。せっかく正解のポイントに入れたとしても、間違った攻め方をしてボウズ
ってことも往々にしてあります

<プリスポーン>
プリスポーンは、産卵を控えたバスが栄養を取るために荒食いする時期です。
成書には、いろいろなルアーに反応するので、広く攻めるルアーを選択するべき
と記載があります。しかし、それはバスボートに乗って広く探るときに当てはま
ることで、フローターやオカッパリではなかなか困難なことです(夜釣りで岸際
に回遊してくるバスを狙うのなら別ですが)。
このときに有効になるのが、コンタクト・ポイントを見極めるということです。
プレスポーンで荒食いをして栄養を蓄えたバスはスポーニング・ベッド(産卵床)
を作る浅場に向かう前に、あるポイントにステイします。これがコンタクト・
ポイントです。沖での荒食いを終えているとはいえ、コンタクト・ポイントにステイ
しているバスの活性は高く、高確率で大型がヒットしてきます。
コンタクト・ポイントは人工的な構造物の場合もあれば、葦際の場合もあります。
フローターやオカッパリでも狙える場所も多いので、それぞれのフィールドでどこが
コンタクト・ポイントなのかを知るバサーだけが至福の時を迎えるのです


コンタクト・ポイントでヒットしたプリスポーンのバス(2010年3月、55㎝、琵琶湖北湖)
コンタクト・ポイントの攻め方は、ピンポイントを狙うので、ワームの釣りが
主体となります。リグの種類は縦に誘うことができるものが良いでしょう。ここに
ステイしているバスは上から落ちてくるものに反応しやすい傾向にあります。
ワームの種類や大きさは千差万別。実際に試してヒットするワームが正解だといえます。
そのフィールドに詳しいバサーに聞くのが一番簡単ですが教えてくれるかどうか

<スポーニング中期>
コンタクト・ポイントから離れたバスは、水深1~2mの浅場に入り、スポー
ニング・ベッドを作り産卵します。このスポーニング中期のバス達は雄雌のペア
か、超大型の雄に複数の雌が付き添っていてハーレムを作っている状態が多いで
すね。

ハーレムを作っていた雄バス(2011年5月、63㎝・6.5lb、乙女が池)

抱卵した雌バス(2011年5月、56㎝・5.5lb、乙女が池)
一度、スポーニング・ベッドを作ったバスはなかなか捕食行動に出ずに、スポー
ニング・ベッドに侵入してくる外敵に攻撃を繰り返します。このバスを食性で釣る
のは非常に困難ですので、この攻撃性を逆手にとって、バスをヒットさせる方法が
あります。
成書にはサスペンドミノーを使い、あたかもスポーニング・ベッドを狙っていると
バスに思わせ、攻撃したときに引っかけるようにヒットさせるとあります。
これも一つの方法ですが、スポーニング・ベッドを守っているバスといえども、
ほんの少し食性は残っているので、それに訴えるリグとルアーを選んでヒットさせる
方法と、攻撃性があるバスをもっと怒らせてヒットに持ち込む方法もあります。
こちらの方がサスペンドミノーを使うよりヒットする確率が高いのですが、ここでは
秘密とさせてください(フィールドでお会いすることがあればご紹介できますが)

<アフタースポーン>
産卵を終えた雌バスは、体力を回復させるために直ぐに沖に移動しますが、長く
スポーニング・ベッドを守っていた雄バスは、体力を回復させるために岸際のスト
ラクチャーにステイします。これがアフタースポーンの雄バスですが、喰い気は
あるものの、かなり警戒心が強く、少しの違和感がだけでヒットしてきません。
オカッパリやフローターでアフタースポーンの雄バスを釣るには、ロングディス
タンス・フィネスが有効です。気配を消して、なるべく遠くから極軽い仕掛けで
バスの前にワームをプレゼンテーションさせます。アクションは小さくしてアピー
ルし過ぎないように気を付けます。当然、ワームは小さめが良いし、カラーも
ナチュラル系が有利だと思います。確率は高くないけれど、ヒットさせることは
できますね。
この時期にヒットするバスは痩せていて、可哀想なくらい貧弱な印象を受けますが、
結構引きは良いですね。

痩せたスレンダーボディの雄バス(2011年6月、56㎝・4lb、琵琶湖北湖)
以上がスポーニングの攻め方ですが、何といっても、コンタクト・ポイントを攻める
のが一番良い方法です。コンタクト・ポイントの見極めが勝敗を決するのです。
☆雌バスの産卵回数は一回だけですか?☆
雌バスは何回産卵をするのかご存じでしょうか?
雌バスは一度に産卵するのではなくて、数回に分けて産卵します。つまり、産卵を
する1個体が何回か、沖→コンタクト・ポイント→スポーニング・ベッド→沖の移動
を繰り返すのです。
ここで、注意するべきは、コンタクト・ポイントにアタリが無くなっても、数日で
第2波、第3波と違うグループがコンタクト・ポイントに入って来て、アタリが復活
するということです。コンタクト・ポイントで良い釣りができる期間は意外と長いの
です。
スポーニング真っ盛りの時に、コンタクト・ポイントがノーマークになっていること
が多いので、チェックするのを忘れないようにしましょう

☆スポーニングは一斉に起こるんですか?☆
スポーニングはその地域一斉で起こる訳ではありません。私の通っているフィールド
でも、10km圏内で、早いところ遅いところで2ヶ月くらいの開きがあります。
それぞれのポイントのスポーニング開始時期を把握していると、美味しい時期を逃さ
なくてすみますね。そして、早いポイントから遅いポイントへ時期をずらして探って
いけば、長い間、デカバスに出会える機会を楽しむことができますよ

次回は、難敵の夏(サマー・シーズン)です。いろいろと誤解も多い時期なのですよ。
2011年12月14日
第1回 はじめに、バスという魚は?
はじめに
バス釣りを始めたのが30歳代だったので、皆さんより遅く始めたため、
強い釣りが体力的に困難だったことと、もともと海で、筏のかかり釣りを
していた関係で、エサ釣りには抵抗がなかったことで、必然的にライトリグ
にのめり込んでいく結果となりました
これといった師匠もおらず、琵琶湖の北湖をホームとして、独学で10年
以上ワーミングを中心にバス釣りをしたおかげで、皆さんの気がつかないと
ころに意外な事実があったと思います。
琵琶湖でしかバス釣りをしていないので、ここで紹介することが、他の
フィールドで通用するとは思いませんが、自分で身につけたことの一部を
ご紹介しましょう。
ビギナーの方やなかなか釣果に恵まれない方は一度、ライトリグを見直して
ください。思わぬ好釣果に恵まれるかも知れませんよ

こんなデカバスに巡り会えたりして(2011年6月、61㎝・8lb、琵琶湖北湖)
さて、今回、第1回として、バス釣りにとって何が一番大切かということ
から始めましょう。
長年バス釣りをしていて、つくづく思うことは、フィールドにバスがいる
ことが一番大切であると言うことです。当たり前だと思われるかも知れない
ですが、意外とこれが分かっていないバサーが多いように思います。
あるポイントに立ったとしましょう。そこにバスがいるかどうかをどうやって
判断しますか?大型のバスボートで魚探を見ながらバスを見つけ出すことなんて
できないオカッパリやフローターですから、どうすればいいのでしょう?
まずは釣ってみて調べてみるというのが一番手っ取り早いですが、これでは
いかにも効率が悪い
釣れなければさっさと見切りを付けて移動を繰り返す。これをラン・アンド・ガン
というようですが、ラン・アンド・ガンするにしても何かの手がかりがあれば、攻め
るべきポイントを絞ることができそうですね。
そこで、大切になるのが、バスの習性を理解することです。相手にしている
魚の習性を知らずに、ただルアーを投げていたのでは思うような釣果を上げる
ことは困難です。相手を知ることはどんな勝負でも大切なことです。
<ブラックバスって?>
北米原産のバスには大きく分けて3種類。ノーザン・ラージマウスバス、
スモールマウスバス、フロリダバスに分かれます。日本で通常ブラックバスと
呼ばれているのはノーザン・ラージマウスバスが多いようです。
 ノーザン・ラージマウスバスは比較的温水を好みますが環境適応性が高く、かなりの低水温でも生息できます。事実、岸に雪が降り積もっているフィールドでも活発にアタって来ます。
ノーザン・ラージマウスバスは比較的温水を好みますが環境適応性が高く、かなりの低水温でも生息できます。事実、岸に雪が降り積もっているフィールドでも活発にアタって来ます。
 フロリダバスは、ノーザン・ラージマウスバスの亜種で、成長が早く、いわゆるポットベリーで、池原ダムなどに生息しています。
フロリダバスは、ノーザン・ラージマウスバスの亜種で、成長が早く、いわゆるポットベリーで、池原ダムなどに生息しています。
 スモールマウスバスは、ラージマウスバスより低水温でクリアな水質を好み、ハイランドレイクなどに生息しています。警戒心が強く、ヒットすればかなりファイトしてくれる好敵手。長野の野尻湖が有名ですね(私は釣ったことがありませんが)。
スモールマウスバスは、ラージマウスバスより低水温でクリアな水質を好み、ハイランドレイクなどに生息しています。警戒心が強く、ヒットすればかなりファイトしてくれる好敵手。長野の野尻湖が有名ですね(私は釣ったことがありませんが)。
バスは肉食魚で典型的なフィッシュ・イーターです。栄養を取るために、魚や
甲殻類を補食して生き延びています。また、警戒心が強い割には好奇心も旺盛で、
いろいろなことに反応します。
この習性を利用するのがルアーフィッシングですが、バスが口を使う行為には、
3種類あるとされています。
第1に、捕食行動です。生命を維持していくためにエサを捕食しなければなりま
せん。そのためにバスは盛んに捕食行動をとります。捕食するエサも多種多様で、
フィールドによってまちまちです。そのフィールドにいるバスが何を捕食している
かを的確に判断することがキモですね。
第2に、自分のテリトリーを守るために他者を攻撃するときに口を使います。
スポーニングベッドを守る雄バスが典型的とされていますが、雌バスでも同様の
行動をとります。なかにはウェダーに体当たりしたり噛みついたりする勇敢なバス
もいます
第3に、バスは好奇心が旺盛だと先程述べましたが、自分の目の前に興味をそそる
ものが通り過ぎても、人間のように手を使って確かめることができません。そのため、
バスはそれを咥えることによって判断します。いわゆるリアクションバイトです。
結構、この行動を取るバスも多い様ですね。
さて、次回はバスの習性のなかでも絶対に理解するべき、シーズナル・パターンに
ついて述べようと思います。
バス釣りを始めたのが30歳代だったので、皆さんより遅く始めたため、
強い釣りが体力的に困難だったことと、もともと海で、筏のかかり釣りを
していた関係で、エサ釣りには抵抗がなかったことで、必然的にライトリグ
にのめり込んでいく結果となりました

これといった師匠もおらず、琵琶湖の北湖をホームとして、独学で10年
以上ワーミングを中心にバス釣りをしたおかげで、皆さんの気がつかないと
ころに意外な事実があったと思います。
琵琶湖でしかバス釣りをしていないので、ここで紹介することが、他の
フィールドで通用するとは思いませんが、自分で身につけたことの一部を
ご紹介しましょう。
ビギナーの方やなかなか釣果に恵まれない方は一度、ライトリグを見直して
ください。思わぬ好釣果に恵まれるかも知れませんよ


こんなデカバスに巡り会えたりして(2011年6月、61㎝・8lb、琵琶湖北湖)
さて、今回、第1回として、バス釣りにとって何が一番大切かということ
から始めましょう。
長年バス釣りをしていて、つくづく思うことは、フィールドにバスがいる
ことが一番大切であると言うことです。当たり前だと思われるかも知れない
ですが、意外とこれが分かっていないバサーが多いように思います。
あるポイントに立ったとしましょう。そこにバスがいるかどうかをどうやって
判断しますか?大型のバスボートで魚探を見ながらバスを見つけ出すことなんて
できないオカッパリやフローターですから、どうすればいいのでしょう?
まずは釣ってみて調べてみるというのが一番手っ取り早いですが、これでは
いかにも効率が悪い

釣れなければさっさと見切りを付けて移動を繰り返す。これをラン・アンド・ガン
というようですが、ラン・アンド・ガンするにしても何かの手がかりがあれば、攻め
るべきポイントを絞ることができそうですね。
そこで、大切になるのが、バスの習性を理解することです。相手にしている
魚の習性を知らずに、ただルアーを投げていたのでは思うような釣果を上げる
ことは困難です。相手を知ることはどんな勝負でも大切なことです。
<ブラックバスって?>
北米原産のバスには大きく分けて3種類。ノーザン・ラージマウスバス、
スモールマウスバス、フロリダバスに分かれます。日本で通常ブラックバスと
呼ばれているのはノーザン・ラージマウスバスが多いようです。
 ノーザン・ラージマウスバスは比較的温水を好みますが環境適応性が高く、かなりの低水温でも生息できます。事実、岸に雪が降り積もっているフィールドでも活発にアタって来ます。
ノーザン・ラージマウスバスは比較的温水を好みますが環境適応性が高く、かなりの低水温でも生息できます。事実、岸に雪が降り積もっているフィールドでも活発にアタって来ます。 フロリダバスは、ノーザン・ラージマウスバスの亜種で、成長が早く、いわゆるポットベリーで、池原ダムなどに生息しています。
フロリダバスは、ノーザン・ラージマウスバスの亜種で、成長が早く、いわゆるポットベリーで、池原ダムなどに生息しています。 スモールマウスバスは、ラージマウスバスより低水温でクリアな水質を好み、ハイランドレイクなどに生息しています。警戒心が強く、ヒットすればかなりファイトしてくれる好敵手。長野の野尻湖が有名ですね(私は釣ったことがありませんが)。
スモールマウスバスは、ラージマウスバスより低水温でクリアな水質を好み、ハイランドレイクなどに生息しています。警戒心が強く、ヒットすればかなりファイトしてくれる好敵手。長野の野尻湖が有名ですね(私は釣ったことがありませんが)。バスは肉食魚で典型的なフィッシュ・イーターです。栄養を取るために、魚や
甲殻類を補食して生き延びています。また、警戒心が強い割には好奇心も旺盛で、
いろいろなことに反応します。
この習性を利用するのがルアーフィッシングですが、バスが口を使う行為には、
3種類あるとされています。
第1に、捕食行動です。生命を維持していくためにエサを捕食しなければなりま
せん。そのためにバスは盛んに捕食行動をとります。捕食するエサも多種多様で、
フィールドによってまちまちです。そのフィールドにいるバスが何を捕食している
かを的確に判断することがキモですね。
第2に、自分のテリトリーを守るために他者を攻撃するときに口を使います。
スポーニングベッドを守る雄バスが典型的とされていますが、雌バスでも同様の
行動をとります。なかにはウェダーに体当たりしたり噛みついたりする勇敢なバス
もいます

第3に、バスは好奇心が旺盛だと先程述べましたが、自分の目の前に興味をそそる
ものが通り過ぎても、人間のように手を使って確かめることができません。そのため、
バスはそれを咥えることによって判断します。いわゆるリアクションバイトです。
結構、この行動を取るバスも多い様ですね。
さて、次回はバスの習性のなかでも絶対に理解するべき、シーズナル・パターンに
ついて述べようと思います。




 Dr.ミーヤンの下手っぴい釣り紀行
Dr.ミーヤンの下手っぴい釣り紀行