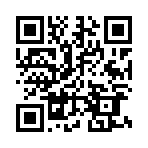2011年12月14日
第1回 はじめに、バスという魚は?
はじめに
バス釣りを始めたのが30歳代だったので、皆さんより遅く始めたため、
強い釣りが体力的に困難だったことと、もともと海で、筏のかかり釣りを
していた関係で、エサ釣りには抵抗がなかったことで、必然的にライトリグ
にのめり込んでいく結果となりました
これといった師匠もおらず、琵琶湖の北湖をホームとして、独学で10年
以上ワーミングを中心にバス釣りをしたおかげで、皆さんの気がつかないと
ころに意外な事実があったと思います。
琵琶湖でしかバス釣りをしていないので、ここで紹介することが、他の
フィールドで通用するとは思いませんが、自分で身につけたことの一部を
ご紹介しましょう。
ビギナーの方やなかなか釣果に恵まれない方は一度、ライトリグを見直して
ください。思わぬ好釣果に恵まれるかも知れませんよ

こんなデカバスに巡り会えたりして(2011年6月、61㎝・8lb、琵琶湖北湖)
さて、今回、第1回として、バス釣りにとって何が一番大切かということ
から始めましょう。
長年バス釣りをしていて、つくづく思うことは、フィールドにバスがいる
ことが一番大切であると言うことです。当たり前だと思われるかも知れない
ですが、意外とこれが分かっていないバサーが多いように思います。
あるポイントに立ったとしましょう。そこにバスがいるかどうかをどうやって
判断しますか?大型のバスボートで魚探を見ながらバスを見つけ出すことなんて
できないオカッパリやフローターですから、どうすればいいのでしょう?
まずは釣ってみて調べてみるというのが一番手っ取り早いですが、これでは
いかにも効率が悪い
釣れなければさっさと見切りを付けて移動を繰り返す。これをラン・アンド・ガン
というようですが、ラン・アンド・ガンするにしても何かの手がかりがあれば、攻め
るべきポイントを絞ることができそうですね。
そこで、大切になるのが、バスの習性を理解することです。相手にしている
魚の習性を知らずに、ただルアーを投げていたのでは思うような釣果を上げる
ことは困難です。相手を知ることはどんな勝負でも大切なことです。
<ブラックバスって?>
北米原産のバスには大きく分けて3種類。ノーザン・ラージマウスバス、
スモールマウスバス、フロリダバスに分かれます。日本で通常ブラックバスと
呼ばれているのはノーザン・ラージマウスバスが多いようです。
 ノーザン・ラージマウスバスは比較的温水を好みますが環境適応性が高く、かなりの低水温でも生息できます。事実、岸に雪が降り積もっているフィールドでも活発にアタって来ます。
ノーザン・ラージマウスバスは比較的温水を好みますが環境適応性が高く、かなりの低水温でも生息できます。事実、岸に雪が降り積もっているフィールドでも活発にアタって来ます。
 フロリダバスは、ノーザン・ラージマウスバスの亜種で、成長が早く、いわゆるポットベリーで、池原ダムなどに生息しています。
フロリダバスは、ノーザン・ラージマウスバスの亜種で、成長が早く、いわゆるポットベリーで、池原ダムなどに生息しています。
 スモールマウスバスは、ラージマウスバスより低水温でクリアな水質を好み、ハイランドレイクなどに生息しています。警戒心が強く、ヒットすればかなりファイトしてくれる好敵手。長野の野尻湖が有名ですね(私は釣ったことがありませんが)。
スモールマウスバスは、ラージマウスバスより低水温でクリアな水質を好み、ハイランドレイクなどに生息しています。警戒心が強く、ヒットすればかなりファイトしてくれる好敵手。長野の野尻湖が有名ですね(私は釣ったことがありませんが)。
バスは肉食魚で典型的なフィッシュ・イーターです。栄養を取るために、魚や
甲殻類を補食して生き延びています。また、警戒心が強い割には好奇心も旺盛で、
いろいろなことに反応します。
この習性を利用するのがルアーフィッシングですが、バスが口を使う行為には、
3種類あるとされています。
第1に、捕食行動です。生命を維持していくためにエサを捕食しなければなりま
せん。そのためにバスは盛んに捕食行動をとります。捕食するエサも多種多様で、
フィールドによってまちまちです。そのフィールドにいるバスが何を捕食している
かを的確に判断することがキモですね。
第2に、自分のテリトリーを守るために他者を攻撃するときに口を使います。
スポーニングベッドを守る雄バスが典型的とされていますが、雌バスでも同様の
行動をとります。なかにはウェダーに体当たりしたり噛みついたりする勇敢なバス
もいます
第3に、バスは好奇心が旺盛だと先程述べましたが、自分の目の前に興味をそそる
ものが通り過ぎても、人間のように手を使って確かめることができません。そのため、
バスはそれを咥えることによって判断します。いわゆるリアクションバイトです。
結構、この行動を取るバスも多い様ですね。
さて、次回はバスの習性のなかでも絶対に理解するべき、シーズナル・パターンに
ついて述べようと思います。
バス釣りを始めたのが30歳代だったので、皆さんより遅く始めたため、
強い釣りが体力的に困難だったことと、もともと海で、筏のかかり釣りを
していた関係で、エサ釣りには抵抗がなかったことで、必然的にライトリグ
にのめり込んでいく結果となりました

これといった師匠もおらず、琵琶湖の北湖をホームとして、独学で10年
以上ワーミングを中心にバス釣りをしたおかげで、皆さんの気がつかないと
ころに意外な事実があったと思います。
琵琶湖でしかバス釣りをしていないので、ここで紹介することが、他の
フィールドで通用するとは思いませんが、自分で身につけたことの一部を
ご紹介しましょう。
ビギナーの方やなかなか釣果に恵まれない方は一度、ライトリグを見直して
ください。思わぬ好釣果に恵まれるかも知れませんよ


こんなデカバスに巡り会えたりして(2011年6月、61㎝・8lb、琵琶湖北湖)
さて、今回、第1回として、バス釣りにとって何が一番大切かということ
から始めましょう。
長年バス釣りをしていて、つくづく思うことは、フィールドにバスがいる
ことが一番大切であると言うことです。当たり前だと思われるかも知れない
ですが、意外とこれが分かっていないバサーが多いように思います。
あるポイントに立ったとしましょう。そこにバスがいるかどうかをどうやって
判断しますか?大型のバスボートで魚探を見ながらバスを見つけ出すことなんて
できないオカッパリやフローターですから、どうすればいいのでしょう?
まずは釣ってみて調べてみるというのが一番手っ取り早いですが、これでは
いかにも効率が悪い

釣れなければさっさと見切りを付けて移動を繰り返す。これをラン・アンド・ガン
というようですが、ラン・アンド・ガンするにしても何かの手がかりがあれば、攻め
るべきポイントを絞ることができそうですね。
そこで、大切になるのが、バスの習性を理解することです。相手にしている
魚の習性を知らずに、ただルアーを投げていたのでは思うような釣果を上げる
ことは困難です。相手を知ることはどんな勝負でも大切なことです。
<ブラックバスって?>
北米原産のバスには大きく分けて3種類。ノーザン・ラージマウスバス、
スモールマウスバス、フロリダバスに分かれます。日本で通常ブラックバスと
呼ばれているのはノーザン・ラージマウスバスが多いようです。
 ノーザン・ラージマウスバスは比較的温水を好みますが環境適応性が高く、かなりの低水温でも生息できます。事実、岸に雪が降り積もっているフィールドでも活発にアタって来ます。
ノーザン・ラージマウスバスは比較的温水を好みますが環境適応性が高く、かなりの低水温でも生息できます。事実、岸に雪が降り積もっているフィールドでも活発にアタって来ます。 フロリダバスは、ノーザン・ラージマウスバスの亜種で、成長が早く、いわゆるポットベリーで、池原ダムなどに生息しています。
フロリダバスは、ノーザン・ラージマウスバスの亜種で、成長が早く、いわゆるポットベリーで、池原ダムなどに生息しています。 スモールマウスバスは、ラージマウスバスより低水温でクリアな水質を好み、ハイランドレイクなどに生息しています。警戒心が強く、ヒットすればかなりファイトしてくれる好敵手。長野の野尻湖が有名ですね(私は釣ったことがありませんが)。
スモールマウスバスは、ラージマウスバスより低水温でクリアな水質を好み、ハイランドレイクなどに生息しています。警戒心が強く、ヒットすればかなりファイトしてくれる好敵手。長野の野尻湖が有名ですね(私は釣ったことがありませんが)。バスは肉食魚で典型的なフィッシュ・イーターです。栄養を取るために、魚や
甲殻類を補食して生き延びています。また、警戒心が強い割には好奇心も旺盛で、
いろいろなことに反応します。
この習性を利用するのがルアーフィッシングですが、バスが口を使う行為には、
3種類あるとされています。
第1に、捕食行動です。生命を維持していくためにエサを捕食しなければなりま
せん。そのためにバスは盛んに捕食行動をとります。捕食するエサも多種多様で、
フィールドによってまちまちです。そのフィールドにいるバスが何を捕食している
かを的確に判断することがキモですね。
第2に、自分のテリトリーを守るために他者を攻撃するときに口を使います。
スポーニングベッドを守る雄バスが典型的とされていますが、雌バスでも同様の
行動をとります。なかにはウェダーに体当たりしたり噛みついたりする勇敢なバス
もいます

第3に、バスは好奇心が旺盛だと先程述べましたが、自分の目の前に興味をそそる
ものが通り過ぎても、人間のように手を使って確かめることができません。そのため、
バスはそれを咥えることによって判断します。いわゆるリアクションバイトです。
結構、この行動を取るバスも多い様ですね。
さて、次回はバスの習性のなかでも絶対に理解するべき、シーズナル・パターンに
ついて述べようと思います。
Posted by ミーヤン at 19:21│Comments(1)
│はじめに
この記事へのコメント
大変参考になります。
新規ブログを楽しみにしております
新規ブログを楽しみにしております
Posted by 名無し at 2013年10月22日 21:44
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。




 Dr.ミーヤンの下手っぴい釣り紀行
Dr.ミーヤンの下手っぴい釣り紀行